北海道のドライブ旅行を計画する中で、「北海道の道の駅ランキング最下位はどこだろう?」と気になったことはありませんか。
インターネット上では、道の駅ワーストや道の駅ワーストランキングといった刺激的な言葉を見かけることもあり、ついクリックしてしまうかもしれません。
しかし、そもそも公式な最下位という順位は存在するのでしょうか。
また、売上が最下位の道の駅はどこ?という素朴な疑問についても、明確な答えはなかなか見つかりません。
この記事では、そうしたランキングの裏側にある真実に迫りつつ、じゃらんの道の駅ランキングで常にランキング1位に輝く人気の施設や、魅力あふれる道央エリアの駅、そして旅の醍醐味であるグルメランキングまで、北海道の道の駅の魅力を多角的に深掘りします。
さらに、北海道の道の駅一覧や、北海道で2025年にオープンする道の駅は?といった最新情報も網羅し、あなたの次の旅がもっと楽しくなる情報をお届けします。
記事のポイント
- 「最下位」ランキングに関する公式情報の有無とその理由
- 売上やネット上の評判に惑わされない道の駅の選び方
- 北海道で本当に人気がある道の駅の具体的な魅力
- 2025年の最新リニューアル・オープン情報と今後のトレンド
北海道の道の駅ランキング最下位は存在する?

- 公式な道の駅ワーストランキングはない
- 売上が最下位の道の駅はどこ?という疑問
- ネット上の道の駅ワースト情報の注意点
- 「最下位」という情報が公式にない理由
- 参考になるじゃらん 道の駅ランキング
公式な道の駅ワーストランキングはない
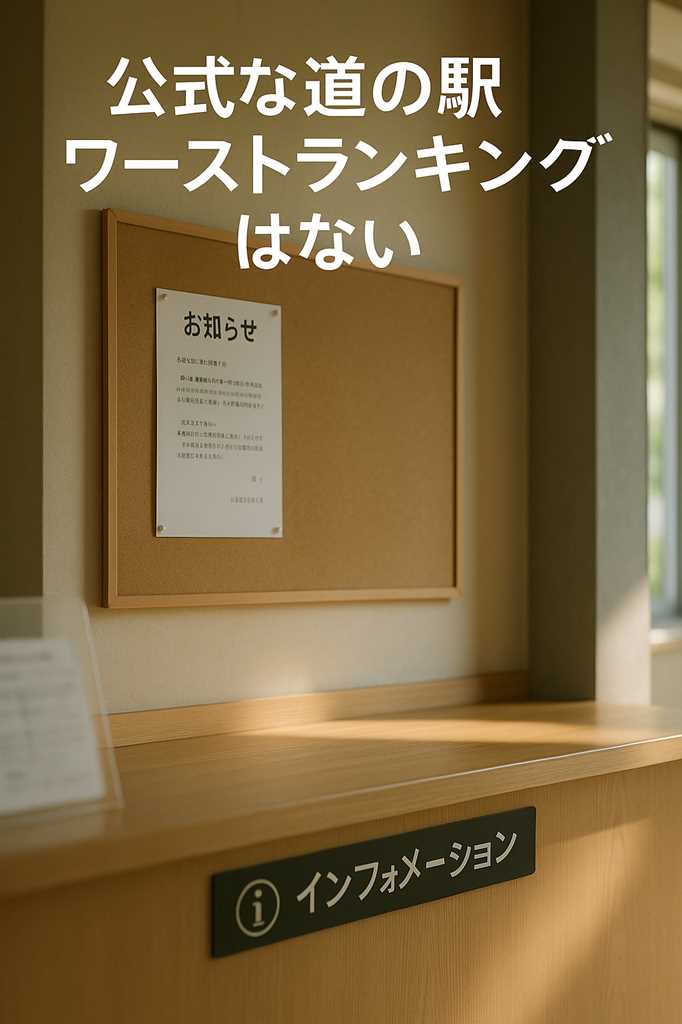
まず最も重要な結論からお伝えすると、国土交通省や地方自治体といった公的機関が公式に発表している「道の駅の最下位ランキング」や、それに類する「ワーストランキング」は一切存在しません。
この事実は、道の駅という施設の成り立ちと目的を理解する上で非常に重要なポイントとなります。
その理由は、道の駅が持つ本質的な「多様性」にあります。
2024年時点で全国に1,200箇所以上存在する道の駅は、一つとして同じものはありません。
例えば、都市近郊の主要幹線道路沿いにある、ショッピングモールさながらの規模を誇る大規模な道の駅を想像してみてください。
そこには複数のレストランや有名ブランドのテナントが入り、多くの来場者で賑わっています。
一方で、山間の静かな集落にひっそりと佇む、無人の野菜直売所が併設されただけの小規模な道の駅も存在します。
これら二つの施設を、単純に「売上高」や「来場者数」といった単一の物差しで比較し、優劣をつけることに果たして意味があるでしょうか。
ランキング指標の落とし穴
仮に道の駅を何らかの基準で評価しようとすると、以下のような矛盾が生じます。
- 売上高や来場者数:
立地条件に大きく左右され、交通量の多い場所にある駅が必然的に有利になります。これは施設の魅力や努力とは必ずしも比例しません。 - 利用者満足度:
評価が個人の目的に依存します。例えば、グルメを求める人、静かな休憩を求める人、家族で遊びたい人では、同じ施設でも満足度は全く異なります。 - 地域貢献度:
雇用の創出、伝統文化の継承、地域イベントの拠点など、貢献の形は多岐にわたり、数値化することが極めて困難です。 - 施設の独自性:
温泉、美術館、キャンプ場といったユニークな付加価値を持つ駅もあれば、あくまでドライバーの安全な休憩に特化したシンプルな駅もあります。これも優劣の問題ではありません。
このように、どの指標を重視するかで順位は大きく変動してしまい、公平で意味のあるランキングを作成することは事実上不可能なのです。
むしろ、言ってしまえば、道の駅を競争させて順位付けを行うという発想自体が、ドライバーの安全確保や地域振興といった、施設の根源的な設置目的とは相容れないものと言えるでしょう。
ポイントの再確認
公式な「最下位ランキング」は存在しない、と覚えておきましょう。
道の駅は商業的な成功を競うための施設ではなく、それぞれの地域を豊かにし、訪れる人々の安全と快適を支えるための拠点であるため、統一基準での順位付けは行われていないのです。
売上が最下位の道の駅はどこ?という疑問

「最下位」というキーワードで情報を探す方の多くは、「経済的に最も成功していない、つまり売上が最も低い道の駅はどこだろう?」という純粋な関心をお持ちかもしれません。
結論から言えば、この疑問に対して明確な答えを得ることはできません。
その最大の理由は、各道の駅の具体的な売上高や詳細な経営状況は、原則として一般には公開されていないからです。
道の駅の運営主体は、市町村が直接管理するケースもあれば、第三セクターや民間企業が指定管理者として運営するケースなど様々です。
これらはそれぞれ独立した事業体であり、その財務情報は企業の内部情報にあたるため、外部に公表する義務がないのです。
このため、特定のメディアが独自の取材や推計に基づいてランキングを作成することはあっても、全国の公式データとして「売上最下位」を断定することは不可能なのです。
ここで一度、視点を変えてみることを提案
「売上が低い」という事実は、必ずしも「その施設の魅力がない」ことには直結しません。
むしろ、大規模な商業主義とは一線を画した、その土地ならではの個性的で尖った魅力を持つ「隠れた名所」である可能性を秘めているのです。
例えば、人里離れた場所にひっそりと佇む小さな駅を想像してみてください。
そこは、もしかしたら売上という指標では下位かもしれません。
しかし、そこには売上だけでは測れない、唯一無二の価値が存在することがあります。
売上だけでは測れない「道の駅」の多様な価値
| 価値のタイプ | 具体的な魅力の例 |
|---|---|
| 専門特化型 | 地元でしか採れない特定の山菜や珍しい果物、あるいは一人の職人が手掛ける工芸品など、「ここでしか手に入らない」という希少価値に特化した施設。品数は少なくても、本物を求める人にとっては宝の山です。 |
| 絶景堪能型 | 物販施設は最小限でも、息をのむような美しい景観を独り占めできる展望台や静かな休憩スペースが整備されている施設。「何もしない贅沢」を味わう体験そのものが価値となります。 |
| 地域密着型 | 観光客向けの派手さはないものの、地元の農家の方々が集まる憩いの場であったり、子供たちの遊び場であったりする施設。旅行者が地域の日常や人の温かさに触れられる貴重な場所です。 |
このように、売上高という一つのものさしだけでは、道の駅が持つ本質的な魅力を見過ごしてしまう可能性があります。
むしろ、「売上が低いかもしれない」ということは、「まだ多くの人に見つかっていない、静かで落ち着いた場所かもしれない」というポジティブな指標と捉えることもできるのです。
旅の目的を「買い物」から「発見」へと少しシフトさせるだけで、ドライブの楽しみは何倍にも広がるでしょう。
ネット上の道の駅ワースト情報の注意点

検索エンジンやSNSを活用すれば、「がっかりした道の駅」や「二度と行かない道の駅」といった個人の体験に基づくいわゆる「ワーストランキング」情報を目にすることがあります。
しかし、これらの情報を旅の計画の参考にする際には、鵜呑みにする前に立ち止まって考えるべき、いくつかの重要な注意点が存在します。
多くの場合、これらのネガティブな情報は、情報の「主観性」と「鮮度」という二つの大きな問題を抱えています。
これを理解せずに情報を信じ込んでしまうと、本来であれば楽しめるはずだった素晴らしい出会いの機会を失ってしまうかもしれません。
【注意点1】評価は個人の「主観」に大きく左右される
まず理解すべきなのは、ネット上の評価は、投稿した個人の「主観的な感想」であるという点です。
例えば、「お土産の種類が少なくてがっかりした」という感想は、多種多様な商品を比較検討して買い物をしたい人にとっては、紛れもないマイナス評価でしょう。
しかし、同じ駅であっても、地元の農家が直接持ち込む新鮮な朝採れ野菜を安く手に入れたい、という目的を持つ人にとっては、そこが「最高の直売所」に映るかもしれません。
このように、道の駅の評価は訪れる人の目的や価値観によって180度変わるものです。
以下の表は、同じ特徴を持つ施設が、目的によってどのように評価が分かれるかを示した一例です。
目的によって変わる評価の具体例
| 施設の特徴 | 目的Aの人の評価(マイナス) | 目的Bの人の評価(プラス) |
|---|---|---|
| 小規模で商品数が少ない | 「品揃えが悪くてつまらない」 (買い物を楽しみたい人) | 「厳選されていて選びやすい」 (特定の特産品を探している人) |
| 建物が古く、レトロな雰囲気 | 「古くて暗い、清潔感がない」 (モダンで快適な施設を求める人) | 「懐かしい雰囲気で落ち着く」 (昔ながらの風情を楽しみたい人) |
| レストランがなく、軽食のみ | 「しっかりした食事ができない」 (ランチを期待していた人) | 「ご当地ソフトクリームが絶品!」 (テイクアウトグルメを楽しみたい人) |
この表から分かるように、ある人にとっての「ワースト」は、別の人にとっての「ベスト」になり得るのです。
【注意点2】情報は常に変化する(情報の「鮮度」)
次に考慮すべきは、情報の「鮮度」です。
道の駅は、静的な施設ではありません。
常に変化し、進化し続けています。
例えば、数年前に「施設が古くて暗い」と酷評された駅が、自治体や地域の努力によって大規模なリニューアル工事を行い、今ではそのエリアで最もモダンで快適な施設に生まれ変わっている、というケースは決して珍しくありません。
また、運営者が変わり、以前は評判の良くなかったレストランが、腕利きのシェフを招き入れたことで地域一番のグルメスポットに変貌を遂げることもあります。
逆もまた然りで、人気だったテナントが撤退してしまうこともあります。
ネガティブな情報に接した際は、それがいつ頃投稿されたものなのか、情報の「タイムスタンプ」を必ず確認する習慣をつけましょう。
数年前の情報は、現在の状況を全く反映していない可能性があることを念頭に置くべきです。
結論:情報の鵜呑みは禁物
ネット上の「ワースト」情報は、あくまで一個人の特定の時点での感想であり、現在の客観的で公式な評価ではありません。
貴重な旅の時間を有意義なものにするためにも、一つの情報だけで判断せず、必ず公式サイトで最新の施設情報を確認したり、複数の異なる口コミを比較検討したりするなど、多角的な視点で判断することが極めて重要です。
「最下位」という情報が公式にない理由
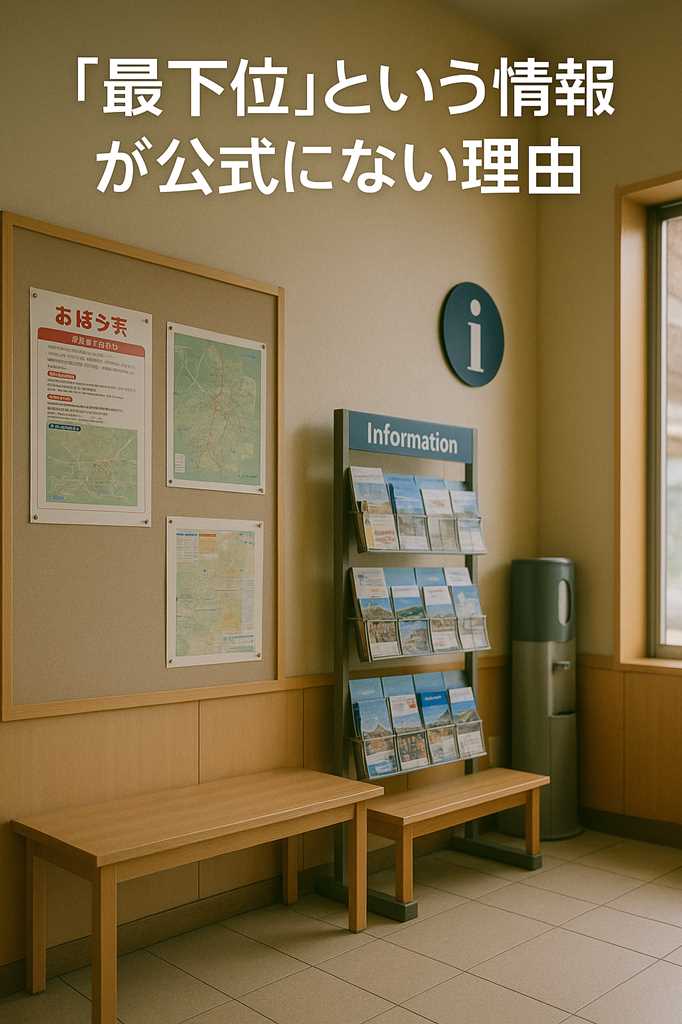
これまで述べてきたように、公式な最下位ランキングが存在しない根底には、道の駅が単なる商業施設ではなく、法律に基づいて設置された公的な役割を持つ施設であるという、極めて重要な事実があります。
この点を理解することが、「最下位」という概念自体が道の駅に馴染まない理由を解き明かす鍵となります。
道の駅は、1993年に道路利用者のための「休憩機能」、道路利用者や地域の人々のための「情報発信機能」、そして「地域連携機能」の3つの機能を併せ持つ施設として創設されました。
国土交通省の公式サイトでも明記されているこれらの機能は、道の駅が単なる通過点ではなく、地域社会における重要な「ハブ(拠点)」であることを示しています。
道の駅が持つ3つの基本機能(詳細版)
| 機能 | 具体的な内容と、その先に目指すもの |
|---|---|
| 1. 休憩機能 | 単に駐車場があるというだけでなく、24時間利用可能な清潔なトイレ、ベビーベッドや授乳室、身体障がい者用設備などを提供することが求められます。これにより、長距離ドライバーや家族連れ、高齢者など、すべての道路利用者が心身ともにリフレッシュし、交通事故の防止に繋げるという社会的な使命を担っています。 |
| 2. 情報発信機能 | リアルタイムの道路交通情報や気象情報はもちろん、地域の観光名所、歴史・文化、イベント情報などを提供します。近年では、災害発生時に防災拠点として機能することも重要視されており、避難情報や支援物資の情報を発信するなど、地域住民の安全・安心を守る情報インフラとしての役割も大きくなっています。 |
| 3. 地域連携機能 | 地域の農家が生産した新鮮な農産物の直売所や、郷土料理を提供するレストラン、特産品を販売する物販所などを運営します。これは単なる物販活動ではなく、地域の産業振興、雇用の創出、そして地域の文化や伝統を次世代に継承するという、より大きな目的を持っています。住民と旅行者が交流する場を提供することで、地域の活性化そのものを促進するエンジンとなることが期待されているのです。 |
(参照:国土交通省「道の駅」案内)
このように、道の駅の評価は、売上という一面的な経済指標だけで測れるものではありません。
例えば、ある道の駅の物販売上が低かったとしても、その駅が地域唯一の災害時避難場所に指定されており、住民の命を守る上で不可欠な存在である場合、その価値は売上高では到底測れません。
言ってしまえば、学校を生徒の学力テストの平均点だけで順位付けするのが無意味であるのと同様に、道の駅を売上だけでランク付けすることもまた、その本質を見誤らせる行為なのです。
それぞれの駅が、その立地や地域の特性に応じて、異なる形で重要な役割を果たしていることを理解することが重要です。
参考になるじゃらん 道の駅ランキング
「最下位」という公式情報がないからといって、どの道の駅を選べば良いか分からない、とがっかりする必要はありません。
むしろ、どの道の駅が多くの人々から支持され、満足度の高い体験を提供しているのかを知るための、信頼できる情報源は存在します。
その代表格と言えるのが、株式会社リクルートが運営する国内最大級の旅行情報サイト『じゃらんnet』や、関連雑誌で毎年発表される「道の駅満足度ランキング」です。
このランキングがなぜ多くの旅行者から信頼されているのか、その理由は明確です。広告や編集部の推測ではなく、実際にその道の駅を訪れた数多くの旅行者から寄せられたアンケートという、リアルな声に基づいて作成されている点にあります。
これは、言わば「行ってよかった」「楽しかった」というポジティブな評価の集合体であり、「人気」を測る上での一つの客観的な指標として非常に参考になります。
選挙で言えば、候補者の演説(自己PR)だけでなく、実際にその候補者に投票した有権者(利用者)の声を聞くようなものですね。
だからこそ、信頼性が高いのです。
例えば、「北海道じゃらん2025年1月号」で発表されたランキングでは、2022年に移転オープンした「道の駅 おとふけ なつぞらのふる里」が、初登場からわずか3年で堂々の総合満足度1位に輝きました。
この事実は、新しい施設であっても、利用者の心を掴む魅力があれば正当に評価されることを示しています。
ランキングを深く読み解くポイント
じゃらんのランキングをさらに有効活用するためには、総合順位だけでなく、その内訳にも注目することが重要です。
通常、アンケートは以下のような複数の項目で評価されています。
- トイレ、無料休憩コーナーの快適さ
- レストランメニュー、テイクアウトメニューの魅力
- 特産品などのお土産の品揃え
- 接客・サービスの質、清潔感
- 各種情報提供の充実度
もしあなたの旅の目的が「美味しいものを食べること」であれば、レストランやテイクアウトの評価が高い駅を、「ユニークなお土産を探すこと」であれば特産品の評価が高い駅をピックアップする、といった使い方ができます。
このように、ランキング情報を活用することで、「最下位はどこか」というネガティブな視点から、「みんなが満足しているのはどこか、そして自分の目的に合うのはどこか」というポジティブな視点へと転換し、あなたにとって「最高の」道の駅を見つけることができるでしょう。

北海道の道の駅ランキング最下位より人気の駅へ
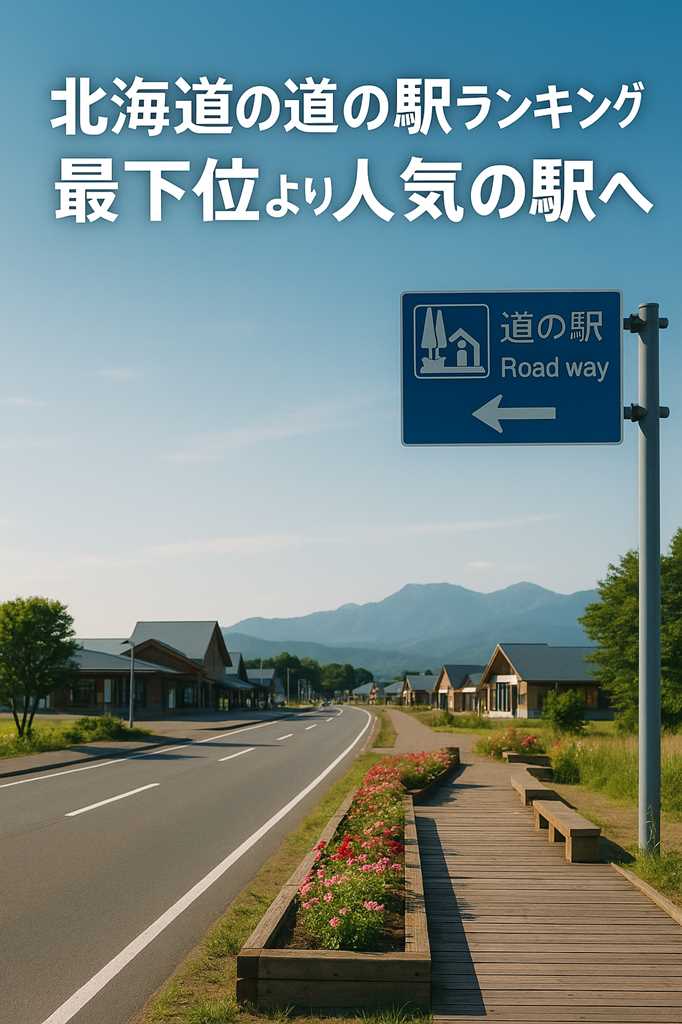
公式な最下位ランキングが存在しないことをご理解いただいた上で、ここからは視点を変え、多くの旅行者から絶大な支持を集める「人気の道の駅」に焦点を当てていきます。
北海道の広大な大地には、訪れる人々を魅了してやまない個性豊かな道の駅が点在しています。
満足度調査で常に上位にランクインする駅の魅力から、最新のオープン情報まで、あなたの旅を豊かにする情報をご紹介します。
- 満足度調査によるランキング1位の道の駅
- 道央エリアで人気の道の駅を紹介
- 北海道の道の駅グルメランキング
- 全129駅!北海道の道の駅一覧
- 北海道で2025年にオープンする道の駅は?
- 北海道の道の駅ランキング最下位を探す際のまとめ
満足度調査によるランキング1位の道の駅

各種メディアや旅行サイトが実施する満足度調査において、常に上位に名を連ね、多くの旅行者から絶大な支持を集める「スター道の駅」が北海道には存在します。
これらの駅は、単に施設が新しい、規模が大きいというだけでなく、景観、グルメ、体験といったそれぞれの分野で、他の追随を許さない圧倒的な個性と魅力を放っています。
ここでは、北海道を代表するトップクラスの人気駅を、その魅力の核心と共に詳しくご紹介します。
【景観部門の絶対王者】道の駅 ぐるっとパノラマ美幌峠
その名の通り、国道243号線の頂点、標高525mの美幌峠に位置するこの道の駅は、何よりもまずその息をのむような大パノラマで知られています。
展望台から眼下に広がるのは、日本最大のカルデラ湖である雄大な屈斜路湖。晴れた日には、湖面に浮かぶ中島(なかじま)、岸辺から白煙を上げる硫黄山(いおうざん)、そして遠くには世界自然遺産・知床連山までをも一望できる、まさに絶景です。
この景色の魅力は、時間や季節によって千変万化する点にもあります。
特に、早朝に訪れると出会える可能性のある「雲海」は、まるで雲の上に立っているかのような幻想的な体験を提供してくれます。
また、夕暮れ時には空と湖面が茜色に染まり、訪れる人々の心に深い感動を刻み込みます。
多くのリピーターが「この景色を見るためだけに来る価値がある」と口を揃えるのも頷けます。
ドライブの合間に、名物の「あげいも」を片手にこの雄大な自然と対峙する時間は、何物にも代えがたい贅沢なひとときとなるでしょう。
【グルメ部門の横綱】道の駅 厚岸グルメパーク
「北海道の旅は、食を追求する旅だ」と考える食通たちを唸らせ、聖地とまで言わしめるのが、牡蠣の名産地・厚岸町にあるこの道の駅です。
その最大の魅力は、一年を通して厚岸産のブランド牡蠣「カキえもん」をはじめとする、獲れたて新鮮な海産物を心ゆくまで味わえることに尽きます。
施設の中心にある魚介市場では、水槽から揚げたばかりの牡蠣やホタテ、カニなどを選んで購入できます。
そして、この駅の真骨頂は、購入した食材を隣接する炭焼きコーナー「炙屋(あぶりや)」に持ち込み、自分たちで炭火で焼いて熱々を食べられるという体験型グルメスタイルにあります。
潮の香りと共に立ち上る香ばしい煙の中で味わう海産物は、まさに絶品。
このエンターテイメント性の高さが、家族連れやグループ客に絶大な人気を誇る理由です。
もちろん、本格的なレストラン「エスカル」では、牡蠣フライやパスタ、ピザなど、シェフが腕を振るう多彩な牡蠣料理をゆっくりと堪能することもできます。
【総合力No.1のニュースター】道の駅 おとふけ なつぞらのふる里
2022年4月に移転オープンし、瞬く間に北海道を代表する人気道の駅の座に躍り出た、まさに新時代の旗手です。
この駅の強みは、特定の分野に特化するのではなく、食、買い物、エンターテインメント、快適性といったあらゆる要素を高次元で満たす「総合力の高さ」にあります。
広大で清潔感あふれるモダンな施設内には、地元十勝の有名店や実力店9つが集結したフードコート「なつぞらダイニング」があり、豚丼からスイーツまで十勝の食の魅力を一堂に味わえます。
また、マルシェ「なつぞら市場」では、朝採れの新鮮な野菜や果物、加工品がずらりと並び、その品揃えと品質の高さは圧巻です。
さらに、NHK連続テレビ小説「なつぞら」のロケセットを忠実に再現したエリアは、ドラマファンならずとも楽しめる人気のフォトスポットとなっています。
誰もが満足できる死角のない施設づくりが、幅広い世代から支持される秘訣と言えるでしょう。
道央エリアで人気の道の駅を紹介

北海道の経済と交通の中心である道央エリアには、札幌や新千歳空港からのアクセスが良く、ドライブコースに気軽に組み込める人気の道の駅が集中しています。
これらの駅は、都市近郊にありながらも、雄大な自然や豊かな食といった北海道らしい魅力を存分に感じられる、洗練された施設が多いのが特徴です。
ここでは、道央エリアを代表する二つの人気駅を深掘りしてご紹介します。
【学びと食のエンターテインメント】道の駅 サーモンパーク千歳
新千歳空港から車でわずか15分という抜群のアクセスを誇り、北海道旅行のスタート地点や最終日に立ち寄る場所として絶大な人気を誇るのが「サーモンパーク千歳」です。
この駅の最大の魅力は、単なる休憩施設に留まらず、「学び」と「食」を融合させた一大エンターテインメント空間である点にあります。
その象徴が、駅に隣接する「サケのふるさと 千歳水族館」です。
ここでは、日本最大級の淡水魚水槽でサケの仲間や北海道の淡水魚の生態を観察できます。
特に、館内にある「水中観察ゾーン」は必見で、ガラス越しに千歳川の川底を直接覗き込むことができ、秋(例年9月から10月頃)には産卵のために遡上してくるサケの群れを間近に観察できる、世界的にも珍しい施設です。
生命の力強さに触れるこの体験は、大人も子供も感動すること間違いありません。
グルメも充実!北海道の食のショーケース
館内には、新鮮な地元野菜が並ぶ直売所はもちろん、北海道を代表するグルメの名店が集結しています。
海鮮丼、スープカレー、ザンギ、そして行列のできるおにぎり専門店など、北海道で食べたいものがここ一箇所でほぼ網羅できると言っても過言ではありません。
旅の短い時間でも、効率的に北海道の味覚を堪能できるグルメスポットとしての機能も、人気の大きな理由です。
家族連れに嬉しい充実のサポート
「サーモンパーク千歳」は、特に小さなお子様連れのファミリー層から高い支持を得ています。
その理由の一つが、知育玩具で有名なボーネルンドが監修した無料のキッズスペースの存在です。
木のぬくもりあふれる空間で、子供たちが安全に、そして創造的に遊べるよう工夫されています。
また、床に投影された映像が人の動きに反応して変化するインタラクティブなプロジェクションマッピングなどもあり、長距離ドライブに飽きてしまったお子様もここでリフレッシュできます。
【花と緑に癒されるガーデンリゾート】道の駅 花ロードえにわ
「花のまち」として全国的に知られる恵庭市にある「花ロードえにわ」は、その名の通り、花と緑に囲まれたガーデンリゾートのような道の駅です。
特に、隣接する広大なガーデンエリア「はなふる」との一体感が最大の魅力で、四季折々の美しい花々が咲き誇る中を散策するだけでも、心が癒されます。
『じゃらん』の全国道の駅グランプリでも常に上位にランクインする実力派で、その洗練された雰囲気から特に女性やカップルからの支持が厚いことで知られています。
この駅を訪れたらぜひ味わいたいのが、地元産の食材を活かしたこだわりのグルメです。
敷地内のベーカリーで焼き上げられるパンは、道産小麦の豊かな風味が人気。また、恵庭産の希少な放牧豚「こな雪とんとん」を贅沢に使った特製スキレットカレーや、季節のフルーツをふんだんに使った彩り豊かなスイーツなど、見た目にも美しいメニューが揃っています。
美しい庭を眺めながら、おしゃれなカフェでランチやティータイムを楽しむ。
そんな優雅な時間を過ごせるのが、「花ロードえにわ」の特別な魅力と言えるでしょう。
北海道の道の駅グルメランキング

北海道の旅において、「食」は絶対に外せない中心的な要素です。
そして道の駅は、その土地ならではの新鮮な食材を活かした絶品グルメを、気取らず手軽に味わえる最高のレストランと言えるでしょう。
ここでは、数多ある道の駅グルメの中でも、各種メディアや口コミで常に高い評価を受け、「これを食べるためだけに、あの道の駅へ行きたい」とまで言われる代表的な逸品を、ランキング形式で深掘りしてご紹介します。
ランキング選定の基準について
このランキングは、特定の調査に基づくものではなく、各種旅行情報サイトの満足度調査、SNSでの口コミ、メディアでの紹介頻度などを総合的に判断し、特に「その土地ならではの体験価値が高い」と評価されるグルメを厳選したものです。
| ランキング | 詳細と魅力 |
|---|---|
| 第1位 道の駅 厚岸グルメパーク(厚岸町) 牡蠣料理 | 「グルメパーク」の名に恥じない、まさに食の殿堂。厚岸湖の豊かな恵みを受けて育つブランド牡蠣「カキえもん」は、小ぶりながらも濃厚でクリーミーな味わいが特徴で、一年中楽しめます。施設内の市場で新鮮な牡蠣を選び、隣接する炭焼きコーナー「炙屋」で自ら焼いて味わう体験は格別です。磯の香りに包まれながら熱々を頬張る瞬間は、最高の旅の思い出となるでしょう。 |
| 第2位 道の駅 望羊中山(喜茂別町) 元祖あげいも | 札幌と洞爺湖を結ぶ中山峠の頂上で、半世紀以上にわたり愛され続ける伝説的なB級グルメ。男爵いもを丸ごと3つ串に刺し、ほんのり甘い特製の衣で揚げた、シンプルながらも奥深い一品です。外はカリッと香ばしく、中は驚くほどホクホク。羊蹄山を望む絶景の中で食べる「あげいも」の味は、多くの道民にとってのソウルフードであり、年間40万本も売れるという実績がその不動の人気を物語っています。 |
| 第3位 道の駅 しらぬか恋問(白糠町) この豚丼 | 「道の駅弁」第1号としても知られる、豚丼の聖地の一つ。地元・白糠町産の厳選された豚肉を使い、一枚一枚丁寧に炭火で焼き上げることで、余分な脂が落ち、肉本来の旨味と香ばしさが最大限に引き出されます。そこに絡むのは、長年継ぎ足されてきた秘伝の甘辛いタレ。このタレが染み込んだ北海道米との相性は抜群で、一度食べたら忘れられない王道の美味しさです。 |
| 第4位 道の駅 なないろ・ななえ(七飯町) ガラナソフト | 北海道民のソウルドリンクとして親しまれる炭酸飲料「コアップガラナ」を練り込んだ、極めてユニークなソフトクリーム。ガラナ特有の爽やかな風味と、ほんのり感じる薬草のような独特の香りが、意外にもミルキーで濃厚なソフトクリームと絶妙にマッチします。「ここでしか味わえない味」としてSNSでも話題沸騰中。話のタ.neとしても、ぜひ一度試してみたい逸品です。 |
これらのグルメは、単に空腹を満たすだけでなく、その土地の風土や歴史、文化までも感じさせてくれる特別な力を持っています。
北海道をドライブする際は、ぜひお腹を空かせて、ご当地ならではの味覚との出会いを楽しんでみてください。
風土や文化を感じさせてくれる特別な一品です。
北海道をドライブする際は、ぜひお腹を空かせて、ご当地ならではの味覚を堪能してみてください。
全129駅!北海道の道の駅一覧

2025年6月現在、北海道には全国の都道府県で最多となる129駅もの道の駅が登録されています。
この圧倒的な数は、日本の道の駅文化において北海道がいかに重要な位置を占めているかを明確に示しています。
広大な北海道の隅々にまで張り巡らされたこの道の駅ネットワークは、長距離移動が多くなる北海道のドライバーにとって、まさに砂漠のオアシスとも言える心強い味方です。
すべての道の駅をここで一つひとつ紹介することは不可能ですが、幸いなことに、旅行者がこれらの情報を効率的に収集できる優れたツールが存在します。
それが、北海道の道の駅の公式情報を発信するウェブサイト「北の道の駅」です。
このサイトでは、全129駅の一覧をインタラクティブな地図上で確認できるほか、以下のような詳細なエリア別に情報を整理して探すことができます。
北海道の6つのエリア区分
- 道南エリア:函館や松前など、歴史と異国情緒あふれる地域。
- 道央エリア:札幌、小樽、新千歳空港を含む、北海道の経済と交通の中心地。
- 道北エリア:旭川、富良野、美瑛など、雄大な大雪山連峰と美しい丘陵地帯が広がる地域。
- オホーツクエリア:網走、紋別など、冬には流氷が訪れる独特の文化を持つ地域。
- 十勝エリア:帯広を中心とした、広大な畑作地帯と美味しい食材の宝庫。
- 釧路・根室エリア:釧路湿原や知床など、手つかずの大自然が残る道東地域。
このようにエリア分けされているため、ご自身のドライブ計画に合わせて、ルート上にある道の駅を効率的にリストアップすることができ、旅の計画を立てる際に非常に便利です。
旅の楽しさを倍増させる「道の駅スタンプラリー」
北海道の道の駅巡りをさらに楽しくする、見逃せない企画が毎年開催されている「北海道『道の駅』スタンプラリー」です。
これは、専用のスタンプブック(有料)を手に、各駅に設置されたオリジナルのスタンプを集めていくというシンプルなものですが、その魅力は絶大です。
スタンプを集めるという明確な目的ができることで、今までなら通過してしまっていたかもしれない町や村に立ち寄るきっかけが生まれます。
そして、そこで思わぬ絶景に出会ったり、美味しいものを見つけたり、地元の人々と交流したりと、旅の体験が格段に豊かになります。
もちろん、スタンプが埋まっていく達成感は格別です。
全129駅の完全制覇を目指す猛者から、特定のエリアだけをのんびり巡る人、あるいは美しいデザインのスタンプだけを集める人まで、楽しみ方はまさに自由自在。
スタンプラリーに参加することで、あなただけの北海道の魅力的な駅がきっと見つかるはずです。
北海道で2025年にオープンする道の駅は?

北海道の道の駅ネットワークは、決して完成されたものではなく、今もなお拡大と進化を続ける「生き物」のような存在です。
既存の施設が時代のニーズに合わせて魅力的なリニューアルを遂げる一方で、地域の新たな起爆剤として、全く新しい道の駅も続々と誕生しています。
これは、旅行者にとって常に新しい発見と出会いの機会があることを意味します。
特に2025年は、北海道の道の駅マップが大きく塗り替わる注目の年となりました。
ここでは、特に話題となった新規オープンおよびリニューアル情報について詳しく解説します。
【新規オープン】注目の新星!「道の駅 ふるびら」(古平町)
2025年4月26日、積丹(しゃこたん)半島の付け根に位置する古平町に、待望の新しい道の駅「ふるびら」が開業しました。
国土交通省の発表によると、この駅は美しい海岸線が続く国道229号沿いにあり、「積丹ブルー」で知られる絶景エリアへの新たな玄関口として大きな期待が寄せられています。
古平町は、ウニやタラコなどの海産物で知られる漁業の町です。
この新しい道の駅では、それら新鮮な海の幸を活かしたグルメや特産品の販売に力を入れており、地域の食文化を存分に発信する拠点となることが期待されています。
積丹半島をドライブする際の新たな立ち寄りスポットとして、多くの観光客で賑わうことでしょう。
【移転・リニューアル】さらなる進化!「道の駅 しらぬか恋問館」(白糠町)
前述の「この豚丼」で絶大な人気を誇る「道の駅 しらぬか恋問館」が、2025年4月29日に、旧施設から約500m帯広寄りの場所へ移転し、パワーアップしてリニューアルオープンしました。
新しい施設は、以前から好評だった太平洋を望む絶景のロケーションはそのままに、駐車場スペースの拡張やトイレの全面的な改修が行われ、ドライバーにとっての快適性が大幅に向上しました。
もちろん、名物の豚丼を提供するレストランもより魅力的になり、地元の特産品を扱う物販コーナーも拡充されています。
長年のファンも、初めて訪れる人も、誰もが満足できる施設へと見事に進化を遂げました。
このように、道の駅は常に変化し続けています。
一度訪れたエリアでも、新しい駅のオープンや既存駅のリニューアルを機に再訪してみると、以前とはまた違った地域の魅力に出会えるはずです。
あなたの「お気に入り」の道の駅も、次に行ったときにはもっと素敵になっているかもしれません。
お出かけ前には公式サイトなどで最新情報をチェックする習慣をつけて、進化し続ける北海道の道の駅を存分に楽しんでください。
北海道の道の駅ランキング最下位を探す際のまとめ
この記事では、北海道の道の駅ランキング最下位というテーマを深掘りし、ランキングの裏側にある事実から、本当に価値のある道の駅の楽しみ方までを解説しました。
最後に、本記事の要点をリスト形式でまとめます。
- 国土交通省などの公的機関が発表する公式な「最下位」や「ワースト」といったランキングは存在しない
- 道の駅は競争ではなく、地域振興やドライバー支援を目的とした公的役割を持つ施設である
- 各道の駅の売上データは一般公開されていないため、売上高による最下位の特定は不可能である
- ネット上の「ワースト」情報は個人の主観や古い情報である可能性が高く、鵜呑みにしないことが重要
- 「最下位」を探すというネガティブな視点ではなく、自分に合った「最高の」道の駅を見つけるという視点が大切
- 信頼できる参考情報として、じゃらんなどの旅行情報サイトが発表する利用者満足度ランキングが挙げられる
- 北海道には「ぐるっとパノラマ美幌峠」(景観)や「厚岸グルメパーク」(グルメ)など、特定の分野で1位に輝く人気の駅が多数存在する
- 道央エリアには「サーモンパーク千歳」や「花ロードえにわ」など、アクセスが良く家族で楽しめる人気の道の駅が集中している
- 「あげいも」や「この豚丼」など、その土地ならではの名物グルメを味わうことは、道の駅巡りの大きな醍醐味である
- 2025年6月時点で、北海道には全国最多となる129駅の道の駅が登録されている
- 公式ウェブサイト「北の道の駅」では、全駅の一覧や最新情報をエリア別に確認できるため、旅の計画に役立つ
- 2025年には「道の駅 ふるびら」の新規開業や、「しらぬか恋問」の移転リニューアルなど、道の駅は常に進化している
- ランキング情報だけに頼らず、各駅の公式サイトで最新情報を確認し、自分の目的に合った駅を選ぶことが後悔しないコツである
- 売上や規模の大小ではなく、それぞれの道の駅が持つ独自の個性や地域との繋がりに目を向けることで、旅はより一層深みを増す
- 最終的に、あなたにとっての最高の道の駅は、あなた自身の興味や目的、そして旅の思い出の中にこそ存在する
参考










