「北海道の方言でありがとうは何て言うの?」と、旅行や交流の際に気になったことはありませんか。
実は、北海道の方言における「ありがとう」は、多くの地域で標準語と同じように使われていますが、その背景や関連する表現には地域性が隠されています。
ありがとうの方言一覧を地方別に見ると、中部地方や静岡、九州、沖縄ではありがとうのかわいい方言や面白い方言があり、その違いは非常に興味深いものです。
この記事では、基本的な北海道方言一覧から、感謝の言葉とセットで気になる北海道の方言で「ごめん」は?という疑問まで、詳しく掘り下げて解説します。
記事のポイント
- 北海道の「ありがとう」の基本的な言い方と文化的背景
- 全国の地方別「ありがとう」の方言一覧とその興味深い特徴
- 意味が面白い、または響きがかわいらしい全国の感謝の方言
- 「ありがとう」と合わせて知っておきたい「ごめん」の北海道での表現
北海道の方言「ありがとう」と全国一覧
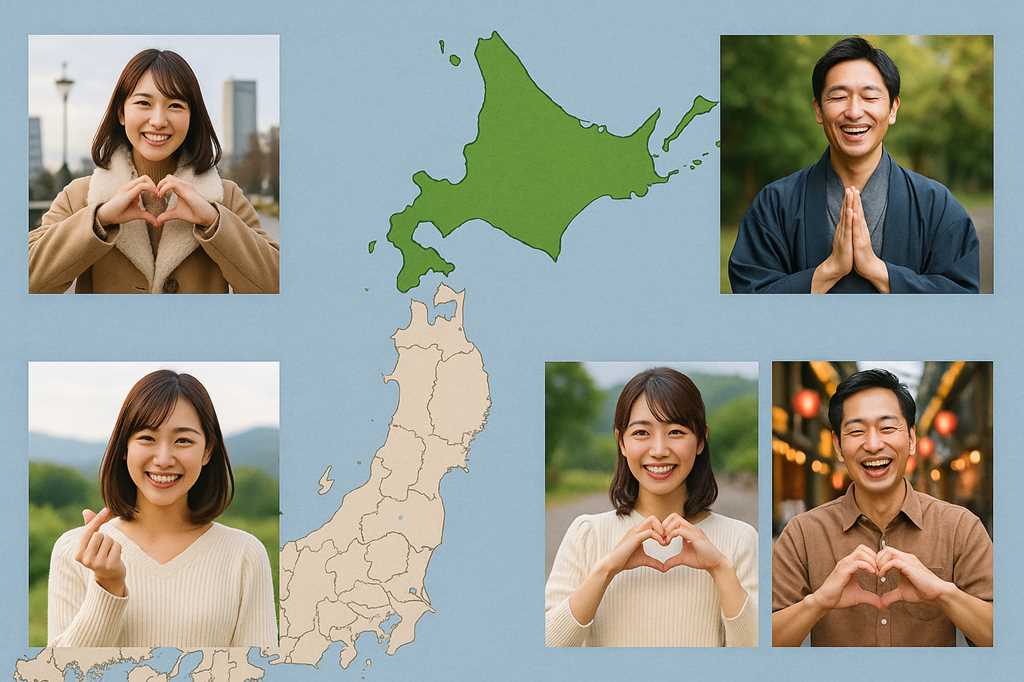
- まずは北海道方言一覧から見てみよう
- 北海道の人がよく使う方言とは?
- 北海道の方言で「ごめん」の言い方
- 全国のかわいい「ありがとう」の方言
- 全国の面白い「ありがとう」の方言
- 全国のありがとうの方言一覧
まずは北海道方言一覧から見てみよう

北海道の言葉と聞くと、「なまら(とても)」や「したっけ(それじゃあ、またね)」といった、独特で温かみのあるフレーズを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、人との繋がりを円滑にする基本の言葉、感謝を伝える「ありがとう」に関しては、少し事情が異なります。
結論から申し上げますと、北海道の大部分では、日常的に標準語の「ありがとう」や、少しくだけた「ありがと」がそのまま使われています。
ただし、全く独自の表現がないわけではありません。
特に、古くから本州との交易で栄えた沿岸部の港町などでは、他の地域の言葉の影響が今なお大切に残されています。
北海道の「ありがとう」関連表現
ありがとう・ありがと
最も一般的で、どの地域・世代にも通じる基本の感謝の言葉です。
旅行中に感謝を伝えたい場面では、安心してこの言葉を使って全く問題ありません。
なんも / なんもなんも
感謝された際の返し言葉として使われる、最も代表的な北海道弁です。
「どういたしまして」「とんでもないです」といった謙遜の気持ちを表しますが、その裏には「そんなことで感謝なんて不要だよ」「お互い様さ」という、相手を気遣う道民の温かい人柄がにじみ出ています。
「なんもさ〜」「なんもだよ」と語尾をつけたり、優しく繰り返したりすることも多く、コミュニケーションを円滑にする魔法の言葉です。
「ありがとう」以外にも、北海道ならではの言葉はたくさんあります。
以下の基本的な北海道方言一覧で、道民の日常会話に少しだけ触れてみましょう。
| 北海道の方言 | 標準語の意味 | 簡単な使い方・ニュアンス |
|---|---|---|
| したっけ | さようなら / それではまた | 友人との別れ際に「じゃあね!」という軽い感覚で「したっけね!」と使います。接続詞の「そうしたら」という意味も持ちます。 |
| なまら | とても / すごく | 「このスープカレー、なまら美味しい!」のように、自分の感情を強調したい時に使われることが多い、若者言葉に近い表現です。 |
| めんこい | かわいい | 主に子どもや小動物など、小さくて愛らしい対象に使われる、どこか懐かしく温かみのある言葉です。 |
| 投げる(なげる) | 捨てる | 「ゴミを投げる」は「ゴミを捨てる」という意味。知らないと「なぜ投げるの?」と驚く方言の代表格です。 |
| (手袋を)はく | (手袋を)する / はめる | ズボンや靴下と同じ「はく」という動詞を使う、北海道独特の面白い言語感覚が表れた表現です。 |
| しゃっこい | (物が)冷たい | 雪や水に触れた時の「ヒヤッ」とする冷たさを表します。「この川の水、しゃっこい!」のように使います。 |
| しばれる | (気温が)非常に寒い | 冬の朝、肌を刺すような凍える厳しさを表現する言葉。「今朝はしばれるねぇ」が冬の挨拶代わりにもなります。 |
このように、北海道の言葉は標準語をベースにしながらも、他の地域からの影響や、厳しい自然環境の中から生まれた独自の表現が豊かに混在しているのが大きな特徴です。
旅行の際には、これらの言葉を少し覚えておくだけで、地元の人々との心の距離がぐっと縮まるかもしれません。
北海道の人がよく使う方言とは?

前述の一覧で基本的な北海道弁を紹介しましたが、ここでは特に道民の日常会話で頻繁に登場する、まさに「ソウルワード」とも言える方言をいくつか深掘りして解説します。
これらの言葉は、単なる言い換えではなく、北海道の気候や人々の気質が反映された、独特のニュアンスを持っています。
使いこなせれば、あなたも「なまら道産子」に近づけるかもしれません。
便利すぎる相槌・同意の「そだねー」
冬季オリンピックのカーリング女子日本代表チームが使ったことで全国的に有名になりました。
強い肯定や否定を避け、相手の意見を柔らかく受け止める、協調性を重んじる道民の気質が表れた言葉です。
イントネーションは語尾を少し上げるのがポイント。
会話の中で相槌として使うと、場が和やかになります。
万能すぎる言い訳(?)の「~さる」
これは標準語に訳すのが非常に難しい、北海道弁の真骨頂とも言える表現です。
「押ささる(意図せず押してしまう)」「書かさる(無意識に書いてしまう)」のように、動詞の後ろにつき、自分の意志とは関係なく、不可抗力でその動作が行われてしまったというニュアンスを表します。
「~さる」の絶妙なニュアンス
例えば、エレベーターで間違った階のボタンを押してしまった時。
標準語では「すみません、押しちゃいました」と自分の非を認めますが、北海道弁では「あっ、押ささった」となります。
これは「押すつもりはなかったのに、なぜか指がボタンに触れてしまった」という、責任をふわりと回避する高度な技術なのです。
説明不能な不快感「いずい」
「いずい」もまた、標準語に一言で置き換えられない言葉です。
「目にゴミが入って、いずい」「この靴、なんだかいずい」のように使われ、「フィットしない」「しっくりこない」「何かおかしい」といった、言葉にしにくい違和感や不快感を表現します。
原因ははっきりしないけれど、とにかく心地が悪い。
そんなモヤモヤした感覚を見事に捉えた言葉です。
めちゃくちゃな状況を表す「わや」
「今日の吹雪はひどくて、道路がもう『わや』だ」のように、「めちゃくちゃ」「手がつけられない」「ひどい状態」を指す言葉です。
元々は関西地方の方言とされていますが、北海道でも広く使われています。
ネガティブな状況で使われることが多いですが、若者の間では「あのライブ、盛り上がりが『わや』だった!」のように、「ヤバい」に近い意味で使われることもあります。
これらの言葉は、北海道の文化や人々の思考様式と深く結びついています。
単語の意味だけでなく、その裏にあるニュアンスを感じ取ることで、北海道への理解がより一層深まるでしょう。
北海道の方言で「ごめん」の言い方

感謝の「ありがとう」と、謝罪の「ごめん」は、円滑な人間関係を築く上で欠かせない車の両輪のような存在です。
北海道旅行中に、もし誰かにぶつかってしまったり、道を尋ねて手間をかけさせてしまったりした場合、どのような言葉で謝意を伝えれば、その気持ちが最もよく伝わるのでしょうか。
この点に関しても、結論としては標準語の「ごめん」や、より丁寧な「ごめんなさい」「すみません」を使うのが最も一般的で確実です。
北海道の言語文化は標準語に近いため、無理に使い慣れない方言で謝罪の言葉を探そうとすると、かえって不自然な印象を与え、誠意が伝わりにくくなる可能性すらあります。
ただし、親しい間柄や、少しくだけた状況では、北海道らしい温かいニュアンスを持つ表現が自然と口から出ることがあります。
「ごめん」に関連する北海道の表現
わりぃね / わりぃ
これは東北地方とも共通する表現で、文字通りには「悪いね」という意味です。
軽い謝罪の気持ちを表す際に使われますが、この言葉の面白い点は、感謝のニュアンスも同時に含まれることです。
「わざわざ手伝ってもらって、わりぃね」といった使い方は、「(あなたに手間をかけさせてしまって)申し訳ない、そして本当にありがとう」という気持ちが凝縮された、非常に温かみのある言葉なのです。
なんも / なんもなんも
前述の通り、これは直接的な謝罪の言葉ではなく、謝罪された側が返す優しさの言葉として非常に頻繁に使われます。
「ごめんね」と謝られた際に、「なんも、気にしないで」「大丈夫だよ」という意味で、「なんもさ」「なんもなんも」と返すのが道民の定番コミュニケーションです。これを覚えておくと、道民とのやり取りがよりスムーズになるでしょう。
「ありがとう」における「おおきに」のような、標準語とは全く異なる「ごめん」を意味する代表的な北海道弁は、実はほとんど使われていません。
コミュニケーションの基本として、まずは誠意を込めて標準語でしっかりと気持ちを伝えることが、最も良い関係を築くための近道です。
その上で、相手が使った方言に耳を傾け、自然な形で現地の言葉に触れていくのが良いでしょう。
全国のかわいい「ありがとう」の方言
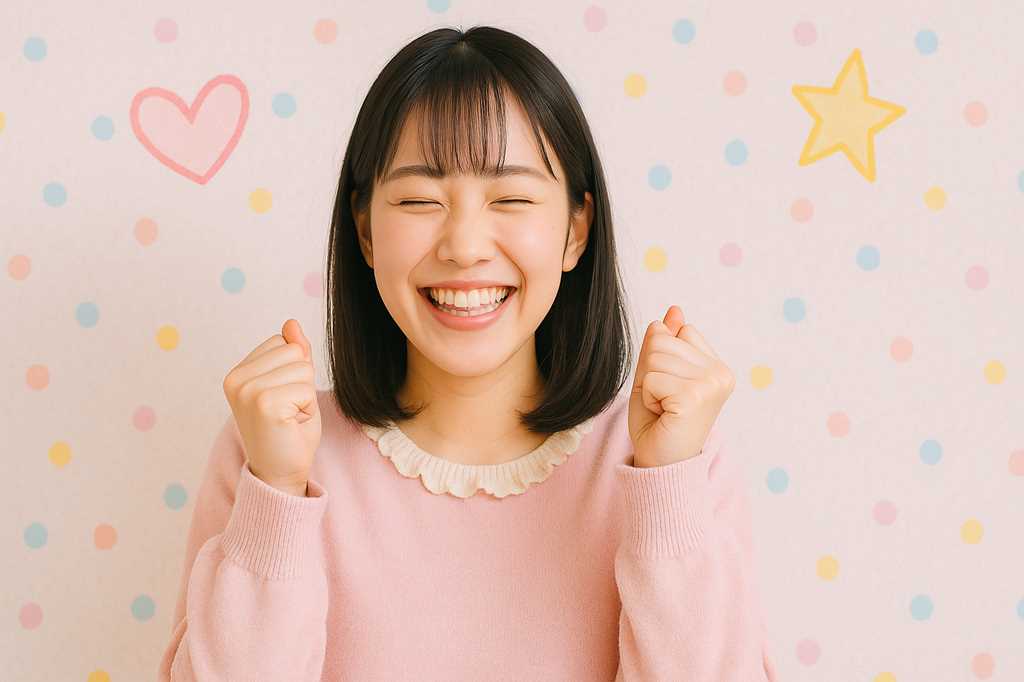
感謝の気持ちを伝える言葉は、その響きによっても受け取る側に与える印象が大きく変わります。
日本全国の「ありがとう」の中には、思わず口にしたくなるような、かわいらしい響きを持つ方言もたくさん存在します。
ここでは、特に親しみやすく、聞いているだけで心が和むような表現をいくつか見ていきましょう。
代表格はやっぱり関西の「おおきに」
「おおきに」は、京都や大阪をはじめとする関西地方で広く使われる、柔らかく優雅な響きを持つ感謝の言葉です。
もともとは「大いに」という意味の副詞で、「おおきに、ありがとう」という言葉が省略された形ですが、その温かい響きと親しみやすさから、多くの人々に愛されています。
「おおきに」のかわいい仲間たち
- おおきんな(三重県):
語尾に付く「な」が、親しみを込めたさらに柔らかな響きを加えており、非常に可愛らしい印象を与えます。 - おぎに(秋田県):
東北特有の訛りが加わることで、どこか素朴で朴訥とした温かみのある音に変化し、心に響きます。
優しさが伝わる山陰地方の「だんだん」
島根県や鳥取県、さらには四国の愛媛県などで使われる「だんだん」も、非常に印象的でかわいい方言です。
この言葉は、もともと「重ね重ね」という意味で、「重ね重ねありがとうございます」という丁寧な表現が時代と共に短くなったものとされています。
言葉の響き自体が優しく、繰り返し発音される音が、感謝の気持ちをより一層深く伝えてくれるようです。
ユニークな響きの東北の言葉
東北地方には、独特の響きを持つ言葉が多くあります。
- もっけだ(山形県庄内地方):
「きのどくな」と同様に「申し訳ない、ありがとう」という謙遜の意味合いを持つ言葉ですが、その音の響きはどこかユニークで愛嬌が感じられます。「もっけだのぉ」と語尾を伸ばして使われることも多く、地元の人々の素朴で優しい人柄が表れているようです。 - ありがとうがんす(岩手県):
語尾の「~がんす」が、どこか古風で丁寧な中にも、親しみやすい愛らしさを感じさせます。
これらの言葉を旅先で少しだけ使ってみることができれば、地元の人々との心の距離もぐっと縮まるかもしれません。
言葉一つで旅の思い出がより色鮮やかになる、それが方言の持つ素敵な力です。
全国の面白い「ありがとう」の方言
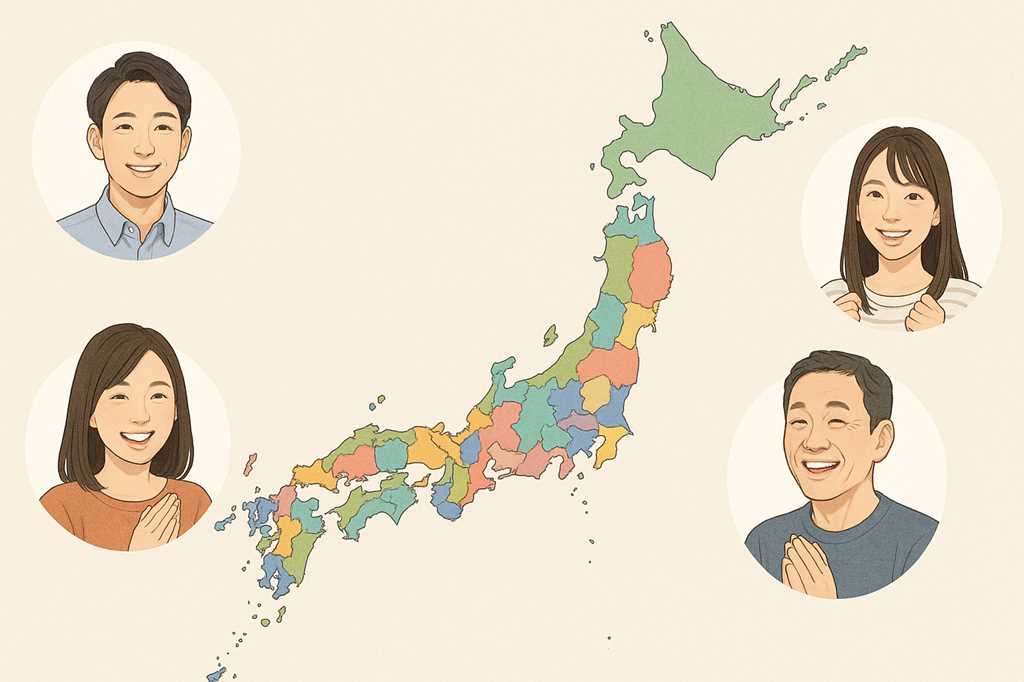
日本全国の「ありがとう」を巡る旅は、時に私たちの常識を覆すような、意味が非常に面白い方言との出会いをもたらしてくれます。
標準語の感覚で聞くと「えっ、どういう意味?」と一瞬戸惑ってしまうかもしれませんが、その言葉が生まれた背景や文化を知ることで、日本の多様性や地域ごとの人々の奥深い気質に触れることができます。
「気の毒だ」が感謝の言葉に?北陸の謙遜が生んだ「きのどくな」
富山県や石川県、福井県といった北陸地方で耳にする「きのどくな」は、紛れもなく感謝を伝える際に使われる代表的な方言です。
標準語で「お気の毒に」と聞くと、相手を不憫に思う、同情するといった意味合いになりますが、北陸では「わざわざすみません、本当にありがとうございます」という、相手への深い気遣いと謙遜の気持ちを込めた感謝の表現として広く定着しています。
何か親切にしてもらった際に、「こんなことまでさせてしまって、あなたの時間や労力を奪ってしまい申し訳ないです。本当にありがとう」という、相手を最大限に思いやる心が、この一言に凝縮されているのです。
旅先での心構え
もし北陸を旅して、親切にした相手から「きのどくなあ」と言われたとしても、決してあなたの行いを非難しているわけではありません。
むしろ、それは心からの深い感謝の表れです。
驚かずに、笑顔で「いえいえ、とんでもないです」と返せると、きっと相手も喜んでくれるでしょう。
「たまったものじゃない」が感謝に?徳島・高知の「たまるか」
徳島県や高知県の一部で使われることがある「たまるか」も、初めて聞くとその意味に驚く方言の一つです。
標準語では「そんなことは到底受け入れられない」「冗談じゃない」といった強い否定や反発を表す言葉ですが、この地域では「こんなによくしてもらって、ありがたくて(うれしくて)たまらない!」という、最高級の感謝や感激を表す際に使われることがあるようです。
一見すると正反対に見える表現が、かえって感謝の気持ちの強さをストレートに伝えています。
これらの面白い方言は、単なる言葉の違いとして片付けるのではなく、その地域の歴史や人々のコミュニケーションのあり方を映し出す鏡のような存在です。
言葉の奥深さに触れることは、旅の大きな醍醐味の一つと言えるでしょう。
全国のありがとうの方言一覧

感謝の気持ちを伝える「ありがとう」という言葉は、日本全国47都道府県で実に多彩な表情を見せてくれます。
ここでは、全国の「ありがとう」の方言を一覧表にまとめました。
あなたの出身地の言葉や、旅してみたい土地の言葉を探してみてください。心温まる言葉の数々が、日本文化の豊かさを教えてくれます。
【ご注意】方言は常に変化しています
この一覧は、各地域の代表的な方言を中心に紹介しています。同じ県内でも地域や世代によって使われる言葉が異なる場合があります。
また、現在では日常的に使われる機会が減った古い表現も含まれていることをご了承ください。
| 地方 | 都道府県 | 「ありがとう」の方言 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | ありがとう、おおきに |
| 東北地方 | 青森県 | ありがとうごす、めやぐだ |
| 岩手県 | ありがとうがんす、おおきに | |
| 宮城県 | ありがとうござりす、どうもね | |
| 秋田県 | ありがとさん、おぎに | |
| 山形県 | ありがとさま、もっけだ | |
| 福島県 | ありがとない、たいへん | |
| 関東地方 | 茨城県 | どうも、あんがと |
| 栃木県 | あんがとね | |
| 群馬県 | ありがと | |
| 埼玉県 | あんがと | |
| 千葉県 | あんがとう | |
| 東京都 | ありがとう | |
| 神奈川県 | ありがとう | |
| 中部地方 | 新潟県 | ごちそうさまです、ありがとね |
| 富山県 | きのどくな、ごちそうさま | |
| 石川県 | きのどくな、ようした | |
| 福井県 | きのどくな、おおきに | |
| 山梨県 | ありがたいこんでごいす | |
| 長野県 | ありがとうござんす | |
| 岐阜県 | きのどく、おおきに | |
| 静岡県 | おおきに、おおきんなあ | |
| 愛知県 | ありがとうさん、おおきに | |
| 近畿地方 | 三重県 | おおきんな |
| 滋賀県 | おおきに、おせんどさん | |
| 京都府 | おおきに | |
| 大阪府 | おおきに | |
| 兵庫県 | おおきに、ありがとうおます | |
| 奈良県 | おおきに | |
| 和歌山県 | おおきによ | |
| 中国地方 | 鳥取県 | だんだん、ようこそ |
| 島根県 | だんだん | |
| 岡山県 | ありがとうござんす | |
| 広島県 | ありがとうあります | |
| 山口県 | たえがとうございます | |
| 四国地方 | 徳島県 | たまるか |
| 香川県 | ありがとう | |
| 愛媛県 | だんだん | |
| 高知県 | たまるか、おおきに | |
| 九州・沖縄地方 | 福岡県 | ありがとう、おおきに |
| 佐賀県 | おおきに | |
| 長崎県 | ありがとうござす | |
| 熊本県 | だんだん、ちょうじょう | |
| 大分県 | おおきに | |
| 宮崎県 | おおきん、だんだん | |
| 鹿児島県 | あいがと、ありがとうごわす | |
| 沖縄県 | にふぇーでーびる |
この一覧を眺めているだけでも、「おおきに」や「だんだん」といった言葉が、特定の地域だけでなく、歴史的な人々の移動や物流のルートに沿って、遠く離れた複数の場所で使われていることがわかります。
言葉が辿ってきた旅路に思いを馳せるのも、方言の面白さの一つですね。
地方別に見る北海道の方言「ありがとう」

- 方言「ありがとう」を地方別に解説
- 中部地方の方言でありがとうの言い方は?
- 静岡の方言でありがとうはどう言うの?
- ありがとうの方言、九州での表現を紹介
- ありがとうの方言、沖縄での独特な言い方
- まとめ:北海道の方言「ありがとう」
方言「ありがとう」を地方別に解説

日本全国に存在する「ありがとう」の方言は、単に言葉が違うというだけではありません。
その一つ一つの言葉の背後には、各地方が歩んできた歴史、育んできた文化、そしてそこに住む人々の気質が色濃く反映されています。
ここでは、特に特徴的な方言を地方ごとにピックアップし、その言葉が持つ深いニュアンスや文化的な背景を少し掘り下げて解説していきます。
方言を深く知ることは、その土地の人々の心に触れるための第一歩です。
表面的な意味だけでなく、言葉に込められた温かい思いを感じ取ることで、旅や人との交流がより一層、豊かで意味のあるものになるでしょう。
方言の三大グループとその背景
全国の多様な「ありがとう」は、その語源や伝播の経緯から、大きく3つのグループに分類できます。
- 「おおきに」グループ
関西で生まれ、北前船などの交易ルートを通じて、日本海側の港町を中心に全国へ広がりました。商人の言葉として定着した歴史があります。 - 「だんだん」グループ
「重ね重ね」という丁寧な言葉が起源とされ、出雲文化圏である山陰地方などに分布しています。誠実な人柄がうかがえます。 - 「きのどくな」グループ
相手への深い気遣いと謙遜の心が表れた、奥ゆかしい北陸地方特有の表現です。
もちろん、これらのグループに属さない、各地域で独自に発展を遂げた言葉も数多く存在します。
次のセクションからは、中部、静岡、九州、沖縄といった地域に焦点を当てて、さらに詳しくその魅力に迫っていきましょう。
中部地方の方言でありがとうの言い方は?

日本のほぼ中央に位置し、多様な文化が絶えず交差してきた中部地方は、「ありがとう」の表現も非常にバラエティに富んでいます。
日本海側、太平洋側、そして内陸の山岳地帯で、それぞれに特徴的な感謝の言葉が使われているのが、この地方の言語文化の面白さです。
前述の通り、この地方を代表する最もユニークな方言が、富山県や石川県、岐阜県の一部で使われる「きのどくな」です。
これは相手への深い気遣いと、迷惑をかけてしまったという申し訳なさを内包した、日本人らしい奥ゆかしい感謝の表現と言えるでしょう。
一方で、愛知県(特に名古屋)や岐阜県、静岡県の一部では、歴史的に関西文化の強い影響を受けて「おおきに」が使われることもあります。
これは、江戸時代から東西の文化と物流を結ぶ交通の要衝であった歴史を、言葉が今に伝えている証拠です。
愛知県の名古屋では「ありがとう」のイントネーションが標準語とは少し異なります。
「り」ではなく「が」にアクセントを置いて「あがとう」のように発音するのが特徴で、地元の人同士の会話では、この微妙な違いが親近感を生むようです。
このように、中部地方と一括りに言っても、その感謝の表現は地域ごとに大きく異なります。
旅をする際には、こうした言葉の違いにも耳を澄ませてみると、その土地が持つ独自の文化や歴史をより深く感じ取ることができるでしょう。
| 都道府県 | 「ありがとう」の方言 | 特徴・ニュアンス |
|---|---|---|
| 新潟県 | ごちそうさまです | 何か物をもらったり、お世話になったりした際に、感謝を込めて使われることがあります。 |
| 富山県 | きのどくな | 「申し訳ない、ありがとう」という謙遜の気持ちが非常に強く表れた言葉です。 |
| 石川県 | きのどくな、ようした | 「ようした」は「よくしてくれたね」といった、親しみを込めた温かい感謝の言葉です。 |
| 山梨県 | ありがたいこんでごいす | 非常に丁寧で、古風な響きを持つ、格式高い感謝の表現と言えます。 |
| 長野県 | ありがとうござんす | こちらも古風で、どこか懐かしい温かみのある丁寧な言い方として知られています。 |
静岡の方言でありがとうはどう言うの?

中部地方の中でも、特に東西の文化が混じり合う静岡県では、「ありがとう」の表現にもそのハイブリッドな特徴が見られます。
地理的に関東と関西のちょうど中間に位置するため、両方の言葉の影響がモザイクのように混在しているのが、静岡の方言の面白い点です。
主な表現としては、関西地方で広く使われている「おおきに」が挙げられます。
これは、江戸時代に日本の大動脈であった東海道を通じて、京や大阪の洗練された文化が直接伝わった名残と考えられています。
特に、愛知県に近い県西部(遠州地方)では、この傾向がより強く見られるようです。
また、「おおきに」が少しだけ変化した「おおきんなあ」という、より親しみを込めた言い方も使われることがあります。
語尾の「なあ」が、静岡らしい穏やかで優しい響きを加えています。
語尾に「~け」が付く可愛らしい表現も
静岡の方言の可愛らしい特徴として、語尾に「~け」や「~っけ」が付くことが挙げられます。
そのため、親しい間柄では「ありがとう」が「ありがとっけねー」というような、少し弾むような明るい響きで使われることもあるようです。
これは友人同士の会話などで聞かれることがあるかもしれません。
もちろん、現代では他の多くの地域と同じように、標準語の「ありがとう」も日常的に使われており、特に若い世代では方言よりも標準語を使うことの方が多くなっています。
しかし、地元の歴史ある商店街などで買い物をした際に、ふとした瞬間にお店の方から温かい「おおきに」という言葉をかけられるかもしれません。
そんな時は、ぜひ笑顔で会釈を返してみてください。言葉を通じて、その土地が歩んできた歴史の一端に触れることができるでしょう。
ありがとうの方言、九州での表現を紹介

「九州男児」という言葉に代表されるように、力強く情に厚いイメージのある九州地方。
その「ありがとう」の表現も、地域ごとの歴史や文化を色濃く反映しており、非常に多様性に富んでいます。
全体的な傾向としては、歴史的に交流の深かった関西の影響を受けた言葉や、各県で独自に発展を遂げた温かみのある言葉が使われています。
九州北部(福岡県、佐賀県、大分県など)では、瀬戸内海を通じて関西との経済的・文化的な繋がりが深かったことから、「おおきに」が広く使われてきました。
現在では標準語の「ありがとう」が主流ですが、年配の方との会話や、昔ながらの市場などでは今でも耳にする機会があるかもしれません。
一方で、熊本県の一部(球磨地方)や宮崎県では、山陰地方などとも共通する「だんだん」という言葉が使われます。
前述の通り、これは「重ね重ね」という意味から来た、非常に丁寧で美しい響きを持つ感謝の言葉です。
そして、九州南部、特に鹿児島県で使われるのが「あいがと」や、より丁寧な「ありがとうごわす」「あいがともさげもす」といった表現です。
「~ごわす」という独特の語尾と相まって、薩摩隼人の力強さと実直さ、そしてその内に秘めた優しさを感じさせます。
九州地方の「ありがとう」方言の例
- 福岡県: ありがとう、おおきに
- 長崎県: ありがとうござす(丁寧な表現)
- 熊本県: だんだん(球磨地方)、ちょうじょう
- 宮崎県: おおきん、だんだん
- 鹿児島県: あいがと、ありがとうごわす
このように、九州を旅する際は、訪れる県によって異なる感謝の言葉に触れることができます。
それぞれの言葉の背景にある歴史や、人々の気質に思いを馳せながらコミュニケーションを楽しむことで、旅の思い出はより一層深まることでしょう。
ありがとうの方言、沖縄での独特な言い方

日本の最南端に位置し、かつては琉球王国として独自の文化と言語を育んできた沖縄県。
その感謝を伝える「ありがとう」も、日本語本土とは大きく異なる、非常に特徴的で美しい言葉が使われています。
沖縄本島で最も一般的に使われ、丁寧な「ありがとうございます」にあたる言葉が「にふぇーでーびる」です。
これは、日常生活の様々な場面で耳にすることができる、沖縄を象徴する言葉の一つです。
友人同士などのよりカジュアルな場面では、シンプルに「にふぇー」と言うこともあります。
「にふぇーでーびる」に込められた深い意味
「にふぇー」の語源には諸説ありますが、「二拝(にはい)」、つまり神仏を二度拝むように、相手に対して深い感謝と敬意を払う気持ちから来ているという説が有力です。
単なる感謝だけでなく、相手へのリスペクトが込められているのです。
言葉の成り立ちからも、沖縄の人々が感謝の心をいかに大切にしてきたかが伝わってきます。
驚くほど多様な島々の言葉
沖縄の言語文化の豊かさと多様性は、本島内にとどまりません。
八重山諸島や宮古諸島など、離島ではそれぞれがさらに独自の言語を発展させてきました。そ
のため、「ありがとう」の表現も島ごとに全く異なります。
- 八重山地方(石垣島など): 「にーふぁいゆー」
- 宮古地方(宮古島など): 「たんでぃがーたんでぃ」
これらの言葉は、同じ沖縄県内でも本島の人には通じないことがあるほど、独自の発展を遂げています。
もし石垣島や宮古島を訪れる機会があれば、その島ならではの感謝の言葉を一つ覚えて使ってみると、地元の人々は大変喜び、心の距離がぐっと縮まるでしょう。
言葉を通じて沖縄のより深く、豊かな文化に触れることは、旅の忘れられない思い出になるはずです。
まとめ:北海道の方言「ありがとう」
この記事では、北海道の方言における「ありがとう」の表現を中心に、全国各地の多様な感謝の言葉とその背景について詳しく解説してきました。
最後に、今回の重要なポイントをリスト形式で総括します。
- 北海道の「ありがとう」は概ね標準語と同じ表現が日常でも用いられる
- 函館など一部では関西文化の影響で「おおきに」が使われる場合がある
- 感謝への返し言葉「なんも」は北海道らしい代表的な返答表現である
- 北海道には「投げる」など面白い方言が多数存在して会話を彩る
- 「ごめん」は基本標準語だが、感謝も滲む「わりぃね」という言い方も用いられる
- 全国には「ありがとう」を表す多様な方言が各地で受け継がれている
- 「おおきに」は関西発祥だが、東北や九州など広域で親しく用いられている
- 「だんだん」は山陰を中心に使われる、重ねて礼を述べる丁寧な感謝表現
- 北陸の「きのどくな」は相手を気遣う謙遜の心を込めた独特の感謝表現である
- 中部地方は東西の文化が交わり、感謝表現も地域差豊かに発達している
- 静岡では関西由来の「おおきに」や親しみある「おおきんなあ」も耳にする
- 九州各地では「おおきに」「だんだん」など多彩で、鹿児島は「あいがと」も定着
- 沖縄の「にふぇーでーびる」は敬意深い感謝を示す、本土と異なる美しい言葉
- 離島ごとに独自の感謝語が伝承され、島々で異なる「ありがとう」が息づいている
- 方言は土地の歴史や暮らしを映す鏡で、言葉を通じ地域文化を深く感じさせる
参考

