北海道旅行や移住を考えたとき、地元の人々が話す言葉に興味を持つことはありませんか。特に、北海道方言の語尾には独特の響きがあり、その意味や使い方を知りたいと感じる方も多いでしょう。北海道は明治時代以降に全国各地からの移住者によって開拓された歴史を持つため、その言葉は東北地方など様々な地域の方言が融合して形成されたという特徴があります。
この記事では、そんな背景を持つ北海道でよく使う方言の語尾を一覧で詳しく解説します。有名な表現はもちろん、かわいい響きのものや、思わず真似したくなる可愛いセリフも例文付きで紹介します。また、道民が自然に使うイントネーションのコツや、実は道外では意味が通じない言葉、さらには上級者向けの表現まで幅広く掘り下げていきます。一見すると意味がなさそうに聞こえる「語尾 さ」の秘密にも迫りますので、ぜひ最後までご覧ください。
記事のポイント
- 北海道方言の代表的な語尾とその意味がわかる
- かわいい方言や具体的なセリフの使い方が学べる
- 日常でよく使う語尾から上級者向け表現まで網羅
- 道民が使う自然なイントネーションのコツを理解できる
特徴的な北海道方言の語尾一覧
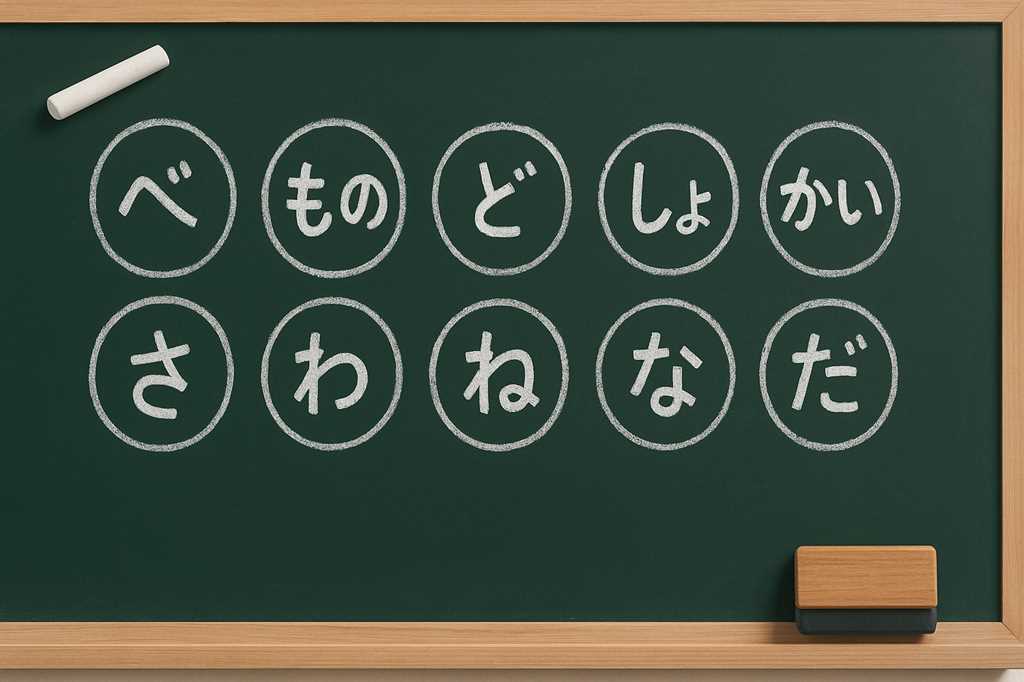
- 北海道弁の語尾一覧を紹介
- 特に有名な語尾とその意味
- 意味を持たない?語尾「さ」の使い方
- 日常でよく使う方言の語尾
- 例文で見る北海道弁の語尾
北海道弁の語尾一覧を紹介
北海道の方言、いわゆる北海道弁には、会話のニュアンスを豊かにする特徴的な語尾が数多く存在します。これらは標準語の「~だよね」や「~しろ」といった表現を、より親しみやすく、あるいは柔らかく伝える役割を果たします。言ってしまえば、これらの語尾を覚えることが、北海道弁を理解する第一歩となるのです。北海道の言葉は、その成り立ちから比較的標準語に近いと言われることもありますが、会話の端々に現れるこれらの語尾こそが、北海道らしさを際立たせる重要な要素と言えるでしょう。
ここでは、まず代表的な語尾を一覧で見ていきましょう。それぞれの語尾が持つ基本的な意味や使われる場面を知ることで、道民の会話がより深く理解できるようになります。
| 北海道弁の語尾 | 標準語の意味 | 主な用途やニュアンス |
|---|---|---|
| ~だべさ、~べ | ~だろう、~だよね | 同意を求めたり、自分の考えを述べたりする時。親しみを込めた表現。 |
| ~しょや、~っしょ | ~でしょう、~だよね | 相手に同意を求める時。「っしょ」はより優しく、柔らかい響き。 |
| ~かい? | ~かい?、~なの? | 相手の様子を尋ねる、意見を聞く時。標準語の「か?」より温かい。 |
| ~だい? | ~どうだい? | 相手の調子や状態を尋ねる時。「どう」とセットで使われることが多い。 |
| ~れ | ~しろ | 命令する時。「食べろ」が「食べれ」になるなど、響きが少し和らぐ。 |
| ~さる | ~してしまう、~できる | 意図しない動作や可能性を表す、非常に便利な表現。 |
| ~でない | ~するな、~しない方がいい | 強い禁止ではなく、優しく諭すようなニュアンス。 |
このように、北海道弁の語尾は微妙なニュアンスを表現するために細かく使い分けられています。例えば、同じ同意を求める表現でも、「~だべ」は自分の意見を少し含んだ主体的な表現であるのに対し、「~っしょ」は相手の意見を尊重し、共感を求めるような優しい響きを持つのです。これらの違いを理解するだけで、道民とのコミュニケーションがより円滑で、深いものになるでしょう。
特に有名な語尾とその意味
北海道弁の中でも、特に知名度が高い語尾がいくつかあります。これらはテレビドラマや映画、さらには全国ニュースで取り上げられることもあり、北海道弁の象徴とも言える表現です。ここでは、その代表格である「~だべさ」と、挨拶にも使われる「したっけ」について、より詳しくその用法と背景を深掘りしていきます。
「~だべさ」「~べ」
「~だべさ」は、「~だろう」「~だよね」という意味で使われる、北海道弁の代名詞的な語尾です。これは自分の考えを述べたり、相手に軽い同意を求めたりする際に用いられます。多くの場合、「だべさ」の3文字全てを使うのではなく、文脈や話す相手との関係性に応じて「~べ」「~だべ」「~べさ」のように柔軟に形を変えて使われます。
例文①(断定):「今日の夜はジンギスカンだべ!」(今日の夜はジンギスカンに決まってるだろう!)
例文②(誘い):「そろそろ飯、食いに行くべ?」(そろそろご飯、食べに行こうか?)
例文③(同意):「やっぱり北海道は冬が一番いいべさ。」(やっぱり北海道は冬が一番いいよね。)
この語尾は親しい間柄で使われることが多く、使うことで会話に温かみとリズムが生まれます。ただし、少しくだけた「田舎っぽい」と捉えられることもあるため、ビジネスシーンや初対面の人との会話など、フォーマルな場面での使用は避けた方が賢明です。
挨拶にもなる「したっけ」
「したっけ」は、本来「そうしたら」「それなら」という意味を持つ接続詞です。しかし、北海道では別れ際の挨拶として「さようなら」「またね」といった意味で非常に広く、そして自然に使われます。これは世代を問わず浸透しており、日常会話に欠かせない言葉の一つです。
「したっけ」の2つの顔
- 接続詞として:「そうしたら」「それなら」
例文:「昨日は疲れて早く寝たんだ。したっけ、今朝はすごく体調がいいさ。」 - 挨拶として:「じゃあね」「またね」「さようなら」
例文:「今日はありがとう!したっけね!」
このように言うと、単なる方言として片付けられない、生活に根付いた文化であることがわかります。特に挨拶としての「したっけ」は、電話を切る間際や店を出る時など、様々な別れの場面で登場します。これらの有名な語尾を覚えておくだけで、北海道への旅行や道民との交流が一段と楽しく、スムーズになるはずです。
意味を持たない?語尾「さ」の使い方

北海道弁を語る上で、非常に特徴的で、かつ標準語話者を少し戸惑わせるのが「さ」という言葉の使い方です。これは文末に付く語尾とは少し異なり、文の途中や文節の終わりに、まるで句読点のように挟み込むように使われます。一聴すると、特に具体的な意味がないように聞こえるかもしれませんが、実は会話のリズムを整えたり、話に注意を引いたり、自分の発言を柔らかくしたりと、非常に重要な役割を担っているのです。
例えば、「昨日さ、スーパーに行ったらさ、すごい人だったんだよ。」のように使います。この「さ」には、標準語の「~ね」に近いニュアンスがあり、聞き手への語りかけや話の区切りを示しています。言ってしまえば、一種の口癖のように聞こえるかもしれませんが、道民の会話では息をするように自然な表現です。これが無いと、どこか冷たく、ぶっきらぼうな印象に聞こえてしまうことさえあります。
「さ」の多用には注意
道民にとっては自然な「さ」の使い方ですが、道外の人がこれを真似しようとすると、不自然に聞こえることが少なくありません。なぜなら、使うタイミングやイントネーション、前後の言葉との繋がりが非常に繊細だからです。「さ」をどこに入れるか、どれくらいの頻度で使うかは、長年の経験によって培われた感覚的なものです。無理に使うと、かえって会話がぎこちなくなる可能性もあるため、まずは聞き手に回って、道民がどのように使っているかをじっくり観察することをおすすめします。
また、この「さ」は単独で使われるだけでなく、「だべさ」や「なんもさ」「なしたのさ」のように他の言葉と結びついて語尾を形成することもあります。このように考えると、「さ」は北海道弁の響きを特徴づける、縁の下の力持ちのような存在と言えるでしょう。
日常でよく使う方言の語尾
北海道民が日常生活の中で、もはや方言だと意識せずに使っている語尾は少なくありません。これらの表現は、道民同士の円滑なコミュニケーションに欠かせないものであり、言葉の裏に親しみや気遣いのニュアンスを含んでいます。ここでは、特に使用頻度の高い「~しょ」と「~かい?」を、その背景とともに詳しく見ていきます。
同意を求める「~しょ」「~っしょ」
「~しょ」や「~っしょ」は、「~でしょう?」「~だよね?」と相手に同意を求める際に使われる、非常にポピュラーな語尾です。「~しょ」が少し強めに念を押したり、当たり前のことを確認したりするニュアンスであるのに対し、「~っしょ」は小さい「っ」が入ることで、より柔らかく、優しい響きになります。
この表現が全国的に有名になったきっかけの一つに、2018年の平昌オリンピックでのカーリング女子日本代表チーム「ロコ・ソラーレ」の活躍があります。彼女たちが試合中に交わした「そだねー(そうだねっしょ)」という言葉は、その愛らしい響きから流行語にもなりました。
例文①(確認):「明日って、会議9時からだったしょ?」(明日って、会議9時からだったよね?)
例文②(共感):「このラーメン、なまら美味しいっしょ?」(このラーメン、すごく美味しいでしょ?)
この語尾は若者から年配の方まで世代を問わず広く使われており、日常会話の至るところで耳にします。相手に何かを勧めたり、自分の意見に共感してほしい時に自然と口から出てくる、まさに「生きた」方言です。
相手を気遣う「~かい?」
「~かい?」は、相手の様子を尋ねたり、意見を聞いたりする際に使われる疑問形の語尾です。「大丈夫かい?」「寒くないかい?」のように、相手を気遣う優しいニュアンスが含まれています。標準語の「~か?」が時として詰問調に聞こえたり、冷たく感じられたりするのとは対照的に、「~かい?」は常に温かく、相手への配慮を感じさせます。
例文:「もう疲れたかい?少し休むかい?」(もう疲れましたか?少し休みますか?)
この表現は、特に年配の方が使うことが多いですが、家族や親しい友人との会話では世代に関係なく使われます。こうして、何気ない一言に思いやりの気持ちを込めるのが、広大で厳しい自然と共に生きてきた北海道の人々の、コミュニケーションスタイルの一つと言えるかもしれません。
例文で見る北海道弁の語尾
ここまで様々な語尾を紹介してきましたが、実際の会話でどのように使われるのかを具体的な例文で見ていきましょう。シチュエーションごとに表現を比較することで、北海道弁の語尾が持つ微妙なニュアンスや、言葉の組み合わせの妙をより深く理解できます。日常の何気ない一コマを想像しながら読んでみてください。
友人との待ち合わせ
A:「ごめん、少し遅れるわ!」
B:「なんもだよ。したって、外はなまらしばれるべ。暖かい格好してきたかい?」(大丈夫だよ。それにしても、外はすごく寒いだろう。暖かい格好してきたかい?)
美味しいものを食べた時
A:「このスープカレー、わやうまいっしょや!」(このスープカレー、すごく美味しいでしょ!)
B:「そだねー。スパイスがきいてて、最高だべさ。家じゃこの味は出せないわ。」(そうだね。スパイスがきいてて、最高だよね。家ではこの味は出せないよ。)
何かを頼む時
A:「悪いけど、そこの醤油とってけれ。」(悪いけど、そこの醤油とってちょうだい。)
B:「はいよ。…あれ、ボタン押したのにテレビつかないわ。これ、押ささらないのかい?」(はいよ。…あれ、ボタン押したのにテレビつかないな。これ、押せないのかな?)
子どもの行動を注意する時
親:「そんなとこでおだつんでない!危ないべさ!」(そんなところでふざけるんじゃない!危ないでしょ!)
子:「したって、面白いんだもん。」(だって、面白いんだもん。)
これらの例文からわかるように、北海道弁の語尾は文脈に応じて様々に組み合わさり、会話にリズムと感情の彩りを加えています。例えば、「~べ」と「~かい?」が同じ文で使われることで、自分の感想と相手への気遣いを同時に表現しています。もし北海道を訪れる機会があれば、ぜひ地元の人々の会話に耳を傾けて、これらの表現が実際に使われている様子を確かめてみてください。
北海道方言の語尾を使いこなす

- かわいい響きの北海道弁
- 思わず使いたい可愛いセリフ集
- 独特なイントネーションに注意
- 実は意味が通じない北海道弁
- 上級者向けの北海道弁
- まとめ:北海道方言の語尾を学ぼう
かわいい響きの北海道弁
北海道弁には、その独特の響きから「かわいい」と評される言葉が多くあります。特に語尾の表現は、標準語に比べて柔らかく、親しみやすい印象を与えるものが少なくありません。厳しい自然環境とは対照的に、どこか温かみのある言葉が人々の心を和ませます。ここでは、多くの人が魅力を感じる「かわいい」北海道弁の語尾や表現に焦点を当ててみましょう。
代表的なのは、やはり「~っしょ」です。「だよね?」と同意を求める際に使われるこの言葉は、小さい「っ」が入ることで、弾むような、どこか愛らしい響きになります。同様に、相手を気遣う「~かい?」も、角のない優しい尋ね方として、温かい人間関係を築くのに役立っています。
響きがかわいい北海道弁の例
- めんこい:「かわいい」を意味する方言の代表格。小さな子供や動物に対して使われることが多いです。
- おっちゃんこ:「座る」という意味の幼児語。「ちゃんとおっちゃんこして」と子供に言う光景は微笑ましいです。
- もちょこい:「くすぐったい」という意味。言葉の響き自体が、くすぐったいような楽しさを感じさせます。
- ばくりっこ:「交換」を意味する「ばくる」から派生した言葉で、「交換しっこ」というニュアンス。子供たちが使うことが多いです。
また、「めんこい」と語尾を組み合わせることで、その魅力はさらに増します。
例文:「この子猫、なまらめんこいっしょ?」(この子猫、すごく可愛いでしょ?)
このように、北海道弁は単語そのものだけでなく、語尾との組み合わせによって、より一層豊かな表情を見せるのです。これらの表現を知ることで、北海道の文化や人々の気質に、少しだけ近づけるかもしれません。
思わず使いたい可愛いセリフ集
北海道弁の魅力を知ると、実際に使ってみたくなるものです。ここでは、日常の様々な場面で使える、可愛らしくて親しみやすいセリフをいくつかご紹介します。これらのフレーズは、ただ単に言葉を置き換えるだけでなく、その裏にある北海道らしい温かい気持ちを伝えるのに役立ちます。覚えておけば、北海道旅行が一層楽しくなること間違いなしです。
可愛いセリフ集
- 「したっけね!」
意味:「またね!」
解説:友人との別れ際に笑顔で使うと、とても親しみがこもった挨拶になります。「バイバイ」よりも温かい響きがあります。 - 「なんもだよ~」
意味:「どういたしまして」「気にしないで」
解説:感謝された時や謝られた時に、この一言を添えると、相手を思いやる優しい気持ちが伝わります。語尾を少し伸ばして、柔らかく言うのがポイントです。 - 「いいんでないかい?」
意味:「いいんじゃないかな?」
解説:何かを提案したり、相手の意見に賛成したりする時に使います。柔らかい響きで、相手を優しく肯定する温かいニュアンスがあります。 - 「なしたのさ?」
意味:「どうしたの?」
解説:相手が落ち込んでいる時などに、心配する気持ちを込めて使います。「さ」が付くことで、より語りかけるような、パーソナルな響きになります。 - 「ゆるくないねぇ」
意味:「大変だね」「きついね」
解説:相手の苦労をねぎらう時に使います。直接的に「大変」と言うよりも、共感している気持ちが伝わる、味わい深い表現です。
もちろん、これらのセリフをいきなり完璧に使いこなすのは難しいかもしれません。しかし、たとえ少しイントネーションが違っていても、一生懸命に現地の言葉を使おうとする気持ちはきっと相手に伝わります。勇気を出して、コミュニケーションのきっかけとして使ってみてはいかがでしょうか。
独特なイントネーションに注意

北海道弁の語尾を自然に使いこなすためには、言葉そのものだけでなく、独特のイントネーション(アクセント)にも注意を払う必要があります。標準語と同じ単語でも、アクセントの位置が違うだけで、全く異なる響きになることがあるのです。これを無視してしまうと、せっかく方言を使ってもどこか不自然に聞こえてしまい、「にわか」だと見抜かれてしまうかもしれません。
例えば、有名な例として「コーヒー」があります。標準語では「コ→ヒ→」と平坦に発音しますが、北海道では「コ↑ーヒー↓」のように、最初の「コ」に強いアクセントが置かれ、その後は下がるように発音されます。これは、語尾についても同様です。
語尾のイントネーションのコツ
相手に質問する際の「~かい?」という語尾は、「か」を強く、少し高めに発音し、「い」は弱く、息を抜くように下げるのがネイティブ流です。「大丈夫かい?」であれば、「だいじょーぶかぁい?」といったイメージです。この微妙な抑揚が、北海道弁らしい柔らかさと親密さを生み出しています。
| 単語 | 標準語のアクセント | 北海道弁のアクセント |
|---|---|---|
| 幼稚園 | よ→うち→えん↓ | よ↑うちえん↓ |
| とうもろこし | と→うもろ→こし→ | と↑うもろこし↓ |
| 五月 | ご→がつ→ | ご↑がつ↓ |
これらのイントネーションは、文章で学ぶよりも、実際に道民の会話を聞いて耳で覚えるのが一番の近道です。もし機会があれば、STVラジオなどの地元の放送局の番組を聞いたり、動画サイトで北海道出身の人の話し方を観察したりするのも良い練習になるでしょう。ただ単に言葉を覚えるだけでなく、その音の響きにも注目することが、北海道弁マスターへの鍵となります。
実は意味が通じない北海道弁
北海道弁の中には、標準語と全く同じ言葉なのに、意味が全く異なるものが存在します。これらは道民にとってはあまりにも当たり前の表現であるため、方言だと気づかずに使っているケースが少なくありません。そのため、道外の人と会話する際に、悪気なく使った一言が思わぬ誤解を生んでしまうことがあります。語尾だけでなく、こうした「隠れ方言」にも注意が必要です。
ここでは、特に誤解を招きやすい代表的な言葉を、その使い方とともに詳しく紹介します。
| 北海道弁 | 北海道での意味 | 標準語の意味 | 解説と例文 |
|---|---|---|---|
| (ゴミを)なげる | 捨てる | 物を投げる | 「このゴミ、なげといて」は「捨てておいて」の意味。物理的に投げるわけではありません。 |
| 手袋をはく | 手袋を着ける | ズボン等を身に着ける | 冬場に「手袋はいてきたかい?」と聞かれても、足ではなく手のことを指しています。 |
| こわい | 疲れた、だるい | 恐ろしい | 「あー、こわい」は疲労の表現。「何が怖いの?」と聞くと話が噛み合わなくなります。 |
| うるかす | 水に浸けておく | (標準語になし) | お米を研いだ後や、汚れがこびりついた食器に「これ、うるかしといて」と言います。 |
| まかす | (液体などを)こぼす | 任せる | 「ジュースまかした!」は「こぼした!」の意味。「任せた」ではありません。 |
| ばくる | 交換する | (標準語になし) | 「席ばくってくれない?」は席の交換の提案。「ばくりっこしよう」は「交換しっこしよう」。 |
これらの言葉に「~べさ」や「~かい?」といった語尾が付くと、さらに複雑になります。例えば、「このお皿、うるかしておいていいかい?」と聞かれた場合、北海道弁を知らなければ意味が全く分からないかもしれません。このようなすれ違いを防ぐためにも、言葉の背景にある生活文化を理解することが大切です。
上級者向けの北海道弁
北海道弁の基本的な語尾や単語をマスターしたら、次はさらに一歩進んだ「上級者向け」の表現に挑戦してみましょう。これらの言葉は、道民以外にはニュアンスを直感的に理解するのが難しく、使いこなすには少し慣れが必要です。しかし、これらを理解できれば、あなたはもう立派な北海道通と言えるでしょう。道民との会話も、より深く、共感に満ちたものになるはずです。
意図しない動作を表す「~さる」
「~さる」は、北海道弁の中でも特にユニークで、道民の思考様式を象徴するような便利な表現です。「押ささる」「書かさる」のように動詞の未然形に付き、「(自分の意思とは関係なく)~してしまう」という、意図しない動作や不可抗力を表します。これは単なる受動態や可能形とは異なる、独特の概念です。
「~さる」のニュアンスの違い
- 標準語:「間違えてボタンを押した。」
→自分の行為であり、責任の所在は自分にある。 - 北海道弁:「間違えてボタンが押ささった。」
→ボタンが"押されてしまった"という感覚。自分の意思とは裏腹に事態が起きたニュアンスで、責任が少し軽く感じられる。
この表現の便利な点は、「自分のせいじゃない」というニュアンスをさりげなく、しかし効果的に伝えられることです。単なる言い間違いや押し間違いも、「押ささった」と言えば、どこか仕方なかったような響きになります。また、「このペン、まだ書かさるかい?」(このペンはまだ書けますか?)のように、「~できる」という可能の意味で使われることもあり、非常に奥が深い表現です。
独特の不快感を表す「いずい」
「いずい」は、標準語に一言で翻訳するのが非常に難しい言葉の代表格です。「目にゴミが入ってゴロゴロする感じ」や「服のタグが首に当たってチクチクする感じ」、「歯に何かが挟まったような違和感」など、体にフィットしない、しっくりこない、微妙な不快感や違和感全般を指します。
この言葉は物理的な感覚だけでなく、精神的な居心地の悪さにも使われます。
例文①(物理的):「新しい靴を履いたら、かかとがいずい。」(新しい靴を履いたら、かかとに違和感がある。)
例文②(精神的):「知らない人ばかりの集まりは、なんだかいずい。」(知らない人ばかりの集まりは、なんだか居心地が悪い。)
この「いずい」という感覚は、道民にとっては非常に共感しやすいものですが、道外の人にそのもどかしい感覚を説明するのは一苦労です。もしあなたがこの言葉の意味を感覚的に理解できたなら、北海道民の心に一歩近づいた証拠かもしれません。
まとめ:北海道方言の語尾を学ぼう
この記事では、北海道方言の語尾について、基本的なものから上級者向けまで、その意味や使い方、そして背景にある文化まで幅広く解説してきました。最後に、本記事の要点をリスト形式で振り返ります。
- 北海道弁の語尾は会話のニュアンスを豊かにする重要な要素である
- 「~だべさ」「~べ」は親しみを込めて同意を求めたり自分の考えを述べたりする時に使う
- 「~しょや」「~っしょ」も同意を求める表現で「っしょ」はより優しく柔らかい響きを持つ
- 「~かい?」「~だい?」は相手を気遣う温かい響きの疑問形の語尾
- 「~れ」は標準語の「~ろ」にあたる命令形だが、響きが少し和らぐ
- 文中に頻繁に挟まれる「さ」は、意味を持たないのではなく会話のリズムを整える役割を持つ
- 「したっけ」は「そうしたら」という接続詞のほかに「またね」という別れの挨拶としても広く使われる
- 「~っしょ」や「めんこい」「おっちゃんこ」など、かわいい響きの言葉が多い
- 「したっけね」「なんもだよ」「いいんでないかい?」はすぐに使える便利なセリフ
- 方言を自然に話すには「コーヒー」などの単語や語尾の独特なイントネーションの理解が重要
- 「ゴミをなげる(捨てる)」「体がこわい(疲れた)」など標準語と意味が異なる単語に注意が必要
- 「~さる」は意図しない動作や可能性を表す、責任を少し回避するニュアンスも持つ便利な表現
- 「いずい」は標準語に一言で訳しにくい、身体的・精神的な微妙な不快感や違和感を示す言葉
- これらの語尾や言葉を学ぶことは、北海道の歴史や文化、人々の気質を理解することに繋がる
- 方言をコミュニケーションのきっかけとして、北海道での人々との交流をより一層楽しもう
参考

